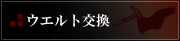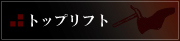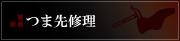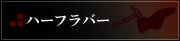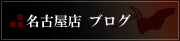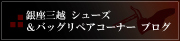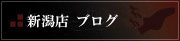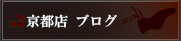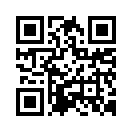2010年04月10日
ハンドソーンウェルテッドとグッドイヤーウェルテッドその2
今回は「ハンドソーンウェルテッドとグッドイヤーウェルテッドその2」をお届けします。
前回はウェルテッド製法についての概要を説明し、ハンドソーンウェルテッド製法とグッドイヤーウェルテッド製法の二つの製法があるとご紹介しました。
そのうち、まずはハンドソーンウェルテッド製法から詳しくご説明したいと思います。
ハンドソーンウェルテッド製法とはズバリ、ウェルトをハンド(手で)ソーン(縫う)製法です。
もっとも原始的な製法であり、グッドイヤーウェルテッド製法の原型となる製法になります。

上記の写真がハンドソーンウェルテッド製法で縫われた靴です。
中底、ウェルト、アッパー、ライニングが白い糸で縫い合わせられています。
白い糸が中底に「直接」縫い付けられているのがお分かりになりますでしょうか?
「直接」と書いたのはのちのちまた意味を持ってくる言葉だからです。
ハンドソーンウェルテッド製法では中底に約5ミリ厚のベンズの革を使用します。
しばらく履いていると、この5ミリの中底が徐々に履いている人の足型に沈んできます。
こうしてその人独自の足型が靴の中底にコピーされ、その人だけによりフィットした一足となるのです。
また、前回「アッパー・ライニング・中底を傷つけずに本底の貼り換え(オールソール)ができる」のがウェルテッドシューズのメリットだと申し上げましたが、ハンドソーンウェルテッドの場合、中底に5ミリの厚さがあるためオールソールの際にもコピーされた足型が消えてしまうことがありません。
つまり、その人だけにフィットしたお靴をずっとお履きいただけるということなのです。
ハンドソーンウェルテッド製法は、フィットした靴をずっと履けるというとってもすばらしい製法なのですが、曲がった針で縫いつけるため、人の手でないと縫うことができません。
つまり、時間とコストはどうしてもかかってしまい、それが価格に反映されて非常に高価な金額のお靴になります。
それゆえ、現在ではビスポーク(注文靴)のようなお靴にしか用いられない製法です。
次回はグッドイヤーウェルテッド製法についてご説明いたします。
前回はウェルテッド製法についての概要を説明し、ハンドソーンウェルテッド製法とグッドイヤーウェルテッド製法の二つの製法があるとご紹介しました。
そのうち、まずはハンドソーンウェルテッド製法から詳しくご説明したいと思います。
ハンドソーンウェルテッド製法とはズバリ、ウェルトをハンド(手で)ソーン(縫う)製法です。
もっとも原始的な製法であり、グッドイヤーウェルテッド製法の原型となる製法になります。

上記の写真がハンドソーンウェルテッド製法で縫われた靴です。
中底、ウェルト、アッパー、ライニングが白い糸で縫い合わせられています。
白い糸が中底に「直接」縫い付けられているのがお分かりになりますでしょうか?
「直接」と書いたのはのちのちまた意味を持ってくる言葉だからです。
ハンドソーンウェルテッド製法では中底に約5ミリ厚のベンズの革を使用します。
しばらく履いていると、この5ミリの中底が徐々に履いている人の足型に沈んできます。
こうしてその人独自の足型が靴の中底にコピーされ、その人だけによりフィットした一足となるのです。
また、前回「アッパー・ライニング・中底を傷つけずに本底の貼り換え(オールソール)ができる」のがウェルテッドシューズのメリットだと申し上げましたが、ハンドソーンウェルテッドの場合、中底に5ミリの厚さがあるためオールソールの際にもコピーされた足型が消えてしまうことがありません。
つまり、その人だけにフィットしたお靴をずっとお履きいただけるということなのです。
ハンドソーンウェルテッド製法は、フィットした靴をずっと履けるというとってもすばらしい製法なのですが、曲がった針で縫いつけるため、人の手でないと縫うことができません。
つまり、時間とコストはどうしてもかかってしまい、それが価格に反映されて非常に高価な金額のお靴になります。
それゆえ、現在ではビスポーク(注文靴)のようなお靴にしか用いられない製法です。
次回はグッドイヤーウェルテッド製法についてご説明いたします。
Posted by リペア工房RESH.日本橋三越本店 at 17:20│Comments(0)
│ウエルト交換
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。